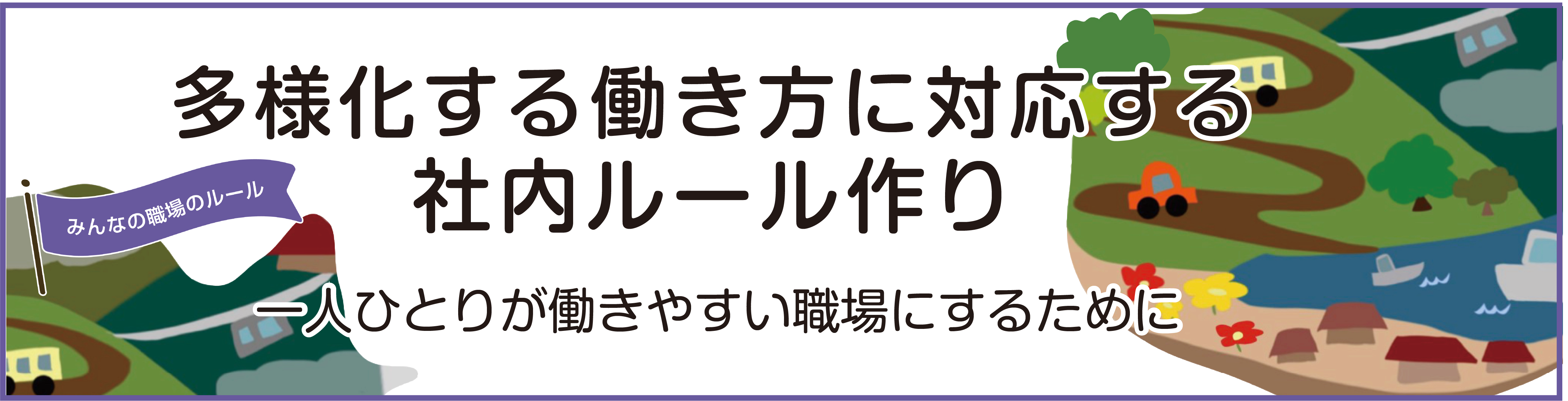「令和4年法改正対応 育児介護休業規程」
この規程に関しては、「育児介護休業法」を軸にして、法律に則った形で作っていきましょう。育児・介護休業を多く取れる会社の方が実際に働く人にとっては理想なので、長く働いてもらうための重要なポイントです。 育児・介護に関する規程は法律上求められる最低限の内容だけでなく、「自社でできる最大限の範囲で、育児・介護している人に働き続けてもらえるルール制定」をぜひ考えてみましょう。
育児介護休業法は令和4年4月及び10月に改正法が段階的に施行されます(令和5年にも施行される部分があります)。 制度としては、今までより育児休業が取得しやすくなります。特に、男性は産前産後休業がありませんが、それを補うように、子の出生後に育休が取れるよう法改正がなされます。
また、育休を分割して取得できるようになったり、育休の申出を行った社員に対しては、会社側から制度の仕組みについて説明しなければならないなど、産休・育休を取得しやすくするための法改正となっています(具体的な改正内容は下記に記載)。
そのため、新たな制度下での休業周りの手続きが円滑に進むように社内体制を整えるとともに、休業を申し出た社員に対して、会社側からの説明義務も発生するようになります。 相談窓口を明確にし、かつ窓口担当者はしっかりと基本的な知識を身に付けることが必要です。
また、産休や育休制度を利用する社員に対して、「育休を取られると周りが迷惑する」などの言動をとったり、嫌がらせ等の行為を行うことは、ハラスメントに該当します。他にも、産休・育休を取得したことを理由に人事評価を悪くしたり、一方的に部署を異動させたりすることもハラスメントとなります。 これらの事態が発生しないよう、会社全体で産休・育休への理解を進めていくことが必須です。
【改正内容】
令和4年4月1日施行
①育児休業を取得しやすい環境の整備の義務化
事業主は、下記いずれかの対応を必ず行わなければなりません。
- (1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- (2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
- (3)社員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- (4)社員へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした社員へ個別の周知・意向確認の措置
- (1)育児休業・産後パパ育休に関する制度
- (2)育児休業・産後パパ育休の申出先
- (3)育児休業給付に関すること
- (4)社員の休業期間中の社会保険料の取り扱い
※面談や書面で周知することが原則ですが、本人が希望する場合はメールやFAXなどでの通知で問題ありません。
令和4年10月1日施行
| 産後パパ育休(R4.10.1~) |
育休制度 (R4.10.1~) |
育休制度 (現行) |
|
| 対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |
| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2 で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
| 1歳以降の延長 | ― | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
| 1歳以降の再取得 | ― | 特別な事情がある場合限り再取得可能※3 | 再取得不可 |
(厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より)
令和5年4月1日施行
社員数1,000人超の企業について育児休業等の取得の状況を年1回公表が義務化